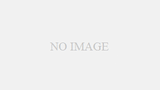2025年2月に開催されたポケモンカードゲーム チャンピオンズリーグ2025 福岡において、意外な組み合わせのデッキが優勝を飾りました。それが「オーダイル & ミロカロスex」デッキです。
水タイプのオーダイル(オーダイルSV5K)をメインアタッカーに据え、ミロカロスexや複数のテクニカルなポケモンを組み合わせたこのデッキは、強力な攻撃性能と巧みな防御・妨害ギミックを併せ持っています。この記事ではデッキの戦略、キーカードの役割、プレイングのポイント、そしてデッキの総括と応用について、詳しく解説します。
1. デッキ概要
基本戦略と狙い:このデッキはオーダイルの爆発的な火力を軸にしつつ、ミロカロスexや他のサポートポケモンの特性で相手の攻撃をいなし、試合を有利に進めることを狙います。具体的には、オーダイルの特性とワザで一撃高火力を叩き込み、ミミッキュやミロカロスexの特性で相手の主力アタッカーのダメージを無効化・抑制しながら戦います。序盤は妨害と盤面作り、中盤以降に大技で逆転するコントロール寄りのミッドレンジデッキと言えるでしょう。
プレイスタイル:一言で言うと「受けと攻めの両立」です。序盤はスボミーのグッズロックやミミッキュの無効化特性で相手の動きを鈍らせ、自分は着々とオーダイルへの進化準備を進めます。盤面が整った中盤以降、一気にオーダイルで高打点を叩き出し、マシマシラの特性やジーランスの特性でオーダイルの弱点(自傷ダメージやワザの連発不可)をカバーします。必要に応じてミロカロスexを前に出し、特定のタイプのポケモンに対して壁として機能させる柔軟性も持っています。派手な一撃と繊細な盤面コントロールを組み合わせたプレイスタイルで、対戦相手の意表を突くことができるデッキです。
2. キーカードの詳細と役割
オーダイル SV5K 015/071 – 主力アタッカー
このデッキのメインアタッカーであるオーダイルは、進化ポケモン(2進化)ながら1エネルギーあたりの火力効率が極めて高いのが特徴です。まず特性「トレントハート」が強力で、自分の番に1回使えます。この特性を使うとオーダイルにダメカンを5個乗せ(自身に50ダメージ), その代わりこの番だけオーダイルの与えるワザダメージを+120することができます。デメリットと引き換えに大幅な火力アップを得る効果で、後述のワザと組み合わせることで凄まじいダメージを出せます。
オーダイルの主力ワザは水エネルギー2個で使える「おおなみ」(大波)で、基本ダメージは160です。このままでも160ダメージと十分ですが、特性「トレントハート」適用下では160+120=280ダメージまで跳ね上がります。
280ダメージは相手の多くのポケモンexを一撃で倒せる数値です。例えばHP280前後のポケモンex(リザードンexなど)も「おおなみ+トレントハート」でワンパン圏内になります。まさに一撃必殺級の火力がオーダイルの最大の強みです。
ただし注意点として、「おおなみ」は一度使うと次の自分の番には使えないという制約があります。毎ターン連続で大技を撃てないため、相手に反撃の隙を与えてしまう恐れがあります。この欠点を補うために、本デッキではジーランスの特性や他のポケモンとの入れ替えによる工夫がなされています(後述)。また、自傷ダメージでHPも削れてしまうため、無理に特性を使うタイミングと温存するタイミングの見極めも重要です。HP180のオーダイルに50ダメージを載せると残り130となり、相手の反撃で倒されやすくもなります。とはいえ、決める場面では思い切って特性+ワザを使い一撃でサイドを2枚取りに行ける爆発力は他に代え難い魅力です。
まとめると、**オーダイルは「高リスク高リターン」**のアタッカーです。上手く扱えばこのデッキの勝ち筋の大半を担ってくれるでしょう。
ミロカロスex SV8 026/106 – サブアタッカー兼ディフェンダー
ミロカロスexはこのデッキのサブアタッカーであり、防御的な役割も持つポケモンです。進化前のヒンバスから1進化するポケモンexで、HP270という非常に高い耐久力を備えています。
最大の特徴は特性「きらめくウロコ」です。この特性により、相手の「テラスタル」のポケモンから受けるワザのダメージや効果をすべて無効にします。つまり、相手のバトル場にテラスタル持ちポケモン(例えば《リザードンex(テラスタル炎)》や《ドラパルトex(テラスタル超)》など)がいる場合、そのポケモンからミロカロスexへの攻撃は一切通らなくなります。
これは相手のデッキによっては完封も狙える強力なメタ性能です。実際、CL福岡でも多く使用されていたテラスタルポケモン(リザードンexやドラパルトex)に対してミロカロスexを前に出すことで、相手は手も足も出なくなる場面がありました。
ミロカロスexは攻撃面でも優秀で、ワザ「ヒプノスプラッシュ」を持っています。水エネルギー1個+無色エネルギー2個の計3エネで160ダメージを与えつつ、相手のバトルポケモンを[ねむり]状態にする追加効果があります(160ダメージ+眠り状態)。160ダメージはオーダイルほどではないものの、中打点としては十分で、多くのたねポケモンexを2発で倒せるラインです。眠り効果も相手に追加の負担を強いるため、奇襲性があります。特に相手が次の番すぐにバトル場のポケモンを引けない場合、眠りで足止めしつつこちらの次の攻撃に繋げられます。
エネルギー管理についてですが、ミロカロスexのワザは要求エネルギーが3個とやや重めです。本デッキでは基本的に水エネルギーを手貼りしていき、リバーサルエネルギーなどの特殊エネルギーで一気に賄う構成になっています。リバーサルエネルギーは自分のサイドが相手より多いときに1枚で3エネぶんとして機能する特殊エネルギーで、ミロカロスexに貼れば一度にワザのエネルギー条件を満たせます。オーダイルもエネルギー要求は水2個なので、序盤に1回サイドを取られ「負けている状況」になれば、リバーサルエネルギー1枚でオーダイルの攻撃準備が完了します。こうした劣勢時の加速も踏まえ、ミロカロスexは中盤以降の逆転プランに組み込まれています。
役割としては、相手のデッキタイプによって「盾」と「矛」両方になれるカードです。例えば相手がテラスタル主体ならミロカロスexを前に出して時間を稼ぎつつ、後続のオーダイルを育てます。一方、相手がオーダイルを倒してサイドを先行した場合、ミロカロスexにリバーサルエネルギーを貼って即座に160ダメージ+眠りで反撃する、といった動きも可能です。2賞ポケモンなので倒されると相手にサイドを2枚与えてしまいますが、その分HPも高く簡単には倒されません。一種の切り札兼クッション役として、このデッキを安定させる重要なポケモンです。
マシマシラ SV6 055/101 – ダメージ変換サポート
マシマシラは、やや特殊な役割を持つ1進化ポケモンです。一見するとデッキのコンセプトに直接噛み合わないように見えますが、その特性「アドレナブレイン」がオーダイルとの相性抜群です。アドレナブレインは、このポケモンに基本悪エネルギーがついているなら使える特性で、「自分の場のポケモン1匹に乗っているダメカンを最大3個まで選び、相手の場のポケモン1匹にのせ替える」という効果です。簡単に言えば、自分のポケモンのダメージを最大30分、相手のポケモンに押し付けることができます。
この特性はオーダイルの自傷ダメージとのコンボを狙ったものです。前述のとおり、オーダイルは特性使用時に自分に50ダメージ(ダメカン5個)を乗せる必要があります。マシマシラがベンチに控えて悪エネルギーが付いていれば、オーダイルに乗った5個のダメカンのうち3個までを相手ポケモンに移すことが可能です。
例えば、バトル場の相手ポケモンにダメカン3個を移せば、その後のオーダイルの「おおなみ」のダメージと合わせて実質+30ダメージの火力強化にもなりますし、ベンチの育成中のポケモンにダメカンを乗せておいて後で倒しやすくするといった使い方もできます。残り2個のダメカンしかオーダイルに残らないため、オーダイル自身の延命にもつながります。
また、マシマシラの特性はオーダイル以外にも応用可能です。例えば、序盤に相手の小ダメージで削られたポケモン(ミロカロスexや別のポケモン)からダメカンを移して相手の主要ポケモンに積み増しすることで、確定数をずらす(次の攻撃で倒せるようにする)といったプレイもできます。特性発動に悪エネルギーが必要なので、このデッキでは基本悪エネルギー1枚が採用されています。場合によってはリバーサルエネルギーをマシマシラに貼ることでも代用できます(リバーサルエネルギーは全てのタイプのエネルギー1個ぶんとしても扱えるため、悪エネ要件を満たせます)。
マシマシラ自体は非ルールのポケモンでHPも高くなく、特性頼みのポケモンです。ドロー補助というよりはダメージ補助の役割ですね。これによりオーダイルのデメリットを帳消しにしつつ、相手に追加ダメージを与える動きが可能となります。特に耐久力の高いポケモンを相手にする際、280ダメージ+特性で乗せ替えた30ダメージ=310ダメージとすることで、例えばHP300超えのポケモンexさえも一撃圏内に押し込むこともできます。地味なサポート役ですが、決まったときの爽快感と試合への影響は大きいでしょう。
その他のポケモン – ミミッキュ、ジーランス、スボミーの採用理由
上記以外にも、このデッキにはユニークなサポートポケモンが数種類投入されています。それぞれ役割がはっきりしているので、一つずつ解説します。
- ミミッキュ(しんぴのまもり):特性「しんぴのまもり」を持つミミッキュは、相手のポケモンex・Vから受けるワザのダメージを一切受けないという非常に強力な能力を持っています
。このデッキでは相手の高火力アタッカーに対する壁役・時間稼ぎとして機能します。例えば相手がミュウexやリザードンexといったポケモンexをエースに据えている場合、ミミッキュをバトル場に出しておけば相手はそのポケモンではミミッキュにダメージを与えられません。その間にこちらはオーダイルを育てたり、次の展開を整えることが可能です。
ただしワザの効果(ダメカンを置く等)は防げない点には注意が必要です。たとえば相手がモンスターボールの効果で別のアタッカーを用意したり、ワザの追加効果でミミッキュ以外に干渉してくる可能性はあります。またミミッキュ自身もワザ「ゴーストアイ」を持ち、超エネルギー1個で相手のバトル場のポケモンにダメカンを7個乗せる攻撃ができます。
ダメージそのものではなくダメカン配置なので、ミミッキュの特性をすり抜けて攻撃できる点も面白いです。もっとも本デッキでは超エネルギーを採用していないため、基本的にミミッキュは攻撃より壁役と割り切って使います。相手にとっては放置できない存在なので、序盤から中盤にかけて相手の動きを遅らせるのに一役買います。 - ジーランス(きおくにもぐる):ジーランスは特性「きおくにもぐる」を持っています。この特性の効果は「ジーランスが場にいる限り、自分の進化ポケモン全員は進化前が持っていたワザを使えるようになる」というものです。
本デッキで進化ポケモンと言えばオーダイル(2進化)とマシマシラ(1進化)、ミロカロスex(1進化)が該当しますが、中でもオーダイル+ジーランスの組み合わせが非常に重要です。オーダイルの進化前であるアリゲイツ(1進化)はワザ「ぎゃくふんしゃ」を持っており、水エネルギー1個で30ダメージを与えた後、このポケモンをベンチポケモンと入れ替えるという効果があります。ジーランスの特性のおかげで、バトル場のオーダイルがこの「ぎゃくふんしゃ」をそのまま使うことが可能になります。具体的には、オーダイルが一度「おおなみ」で攻撃した次のターンに、ジーランス特性で解禁された「ぎゃくふんしゃ」をオーダイルで撃つことで、オーダイル自身がベンチに下がることができます。
これにより「おおなみが次の番に使えない」という制約をリセットしつつ、オーダイルを前線から退避させることが可能となります。退避後は別のポケモン(例えば特性で無敵効果を持つミミッキュなど)をバトル場に繰り出せますから、相手の反撃を受け流しつつ次ターンに再びオーダイルをベンチに戻す…というヒット&アウェイ戦術が実現します。これはオーダイルの継戦能力を高める上で非常に重要なテクニックです。
基本的には特性を場に置いておくだけで機能するため、ベンチ要員として割り切ってOKです。HPが低めなので、相手のボスの指令などで倒されないよう注意は必要ですが、仮に倒されてもサイド1枚しか取られないため割り切りやすいです。このようにジーランスは、オーダイルのワザ制限をケアしゲームプランの柔軟性を上げる縁の下の力持ちと言えます。 - スボミー(むずむずかふん):スボミー(=スボミーSV8a)は種ポケモンで、ワザ「むずむずかふん」を持っています。驚くべきはこのワザ、エネルギーなしで使用可能でダメージこそ10ですが、次の相手の番、相手は手札からグッズを出して使えないという強力な効果を与えます。いわゆるグッズロックを能動的に仕掛けられるカードです。しかもスボミーは逃げエネルギーが0(にげるコスト無料)なので、攻撃後にベンチに下がりやすいのも優秀なポイントです。チャンピオンズリーグ福岡でも各所でスボミーが活躍し、「大会中実に大量の花粉(=むずむずかふん)が飛び交った」と言われるほど多くのデッキに採用されていました。
本デッキでは序盤の妨害役としてスボミーが採用されています。例えば後攻1ターン目、相手が展開を始めようとするタイミングでスボミーの「むずむずかふん」を決めれば、次の相手ターンは展開用グッズが一切使えなくなります。その隙にこちらは種ポケモンをベンチに並べたり、サポートを使って手札を整えたりできます。ノーコストで撃てる先攻潰しワザとして極めて有用で、スボミー自身は攻撃後すぐ逃げてベンチに下がれるため(逃げ0が大きな利点)、その後はオーダイルや他のアタッカーにバトンタッチしやすいです。
グッズロック下では相手はグッズによる切り返しができずサポート頼みになるので、1ターンのテンポをこちらに引き寄せることができます。スボミーはHPも低く倒されやすいですが、倒されてもサイド1枚なので割り切れますし、逆に相手がスボミーを倒すために1ターン使ってくれれば儲けものです。序盤の時間稼ぎ兼攪乱要員として、採用価値の高いカードです。
以上のように、ミミッキュは「相手の高火力を無効化する盾」、ジーランスは「こちらの戦略を拡張する潤滑油」、スボミーは「序盤の奇襲妨害役」と、それぞれ明確な役割があります。どれも1枚差しのテクニカルなカードですが、環境に刺さる効果やデッキ内部でのシナジーを持っており、優勝リストではしっかりとその効果を発揮しました。
トレーナーズ・グッズの役割 – ポケギア3.0、カウンターキャッチャー 他
このデッキを支えるトレーナーズ(グッズ)も特徴的なカードが採用されています。特に注目すべきはポケギア3.0とカウンターキャッチャーの存在で、いずれも特殊な効果でデッキの動きを安定・強化させます。
- ポケギア3.0:山札の上7枚を見て、その中のサポートを1枚手札に加えるグッズです。サポートは1ターンに1度しか使えませんが、欲しいタイミングで欲しいサポートカードを引き込むことができればゲームメイクが飛躍的に楽になります。本デッキにはナンジャモやペパー、ボスの指令など状況によって使い分けたいサポートが複数投入されています。ポケギア3.0があれば、例えば序盤にドローサポート(博士の研究やペパー)が欲しいとき、あるいは中盤以降にナンジャモで相手の手札リセットを狙いたいときなどに山札から引き当てる確率を上げられます。要はデッキの動きを安定させる潤滑油であり、1~2枚採用しておくことで「欲しいサポートが引けない」という事故を減らしています。特にこのデッキのように1枚差しのサポートが多い場合、ポケギアで目的のカードにアクセスできるかどうかで展開力が大きく変わるため重要です。
- カウンターキャッチャー:このカードはサイド枚数が相手より多い(=自分が負けている)ときにしか使えませんが、その条件下では相手ベンチの好きなポケモンをバトル場に引きずり出すことができます。効果自体は「ボスの指令」に似ていますが、グッズであるため手札から何枚でも使える点が強力です。つまり、同じターンにナンジャモ(あるいは博士の研究など)を使いながら、さらにカウンターキャッチャーでボス効果を使う…といった芸当が可能になります。このデッキは序盤にスボミーやミミッキュなどの1サイドポケモンを場に出す関係で、先に相手にサイドを取られる展開になりやすいです。逆に言えば中盤以降自分がサイドで負けている状態であることも多く、そのタイミングでカウンターキャッチャーが輝きます。例えば一度相手に2サイド先行された状況で、カウンターキャッチャーを使い相手ベンチの要(育成途中のや特性持ちのサポートポケモンなど)を呼び出し、オーダイルの大技で倒す…といった動きが決まれば、一気にサイド逆転が狙えます。この「劣勢からの一発逆転カード」としてカウンターキャッチャーは非常に優秀で、コントロール寄りのデッキには複数枚投入されることもあります。
また、グッズゆえに同じターンにサポートのナンジャモ(手札干渉)と組み合わせられるのも極めて強力です。ナンジャモで相手の手札を減らしつつ、カウンターキャッチャーで欲しい獲物を引っ張り出し、オーダイルで倒すというコンボは、CL福岡の決勝戦でも炸裂しました。ボスの指令は通常サポート権を使ってしまうため、使うとそのターン他のサポートが使えません。一方でカウンターキャッチャーならそれがないので、デッキの他の動きと両立して相手の要を潰せるのが強みです。 - 夜のタンカ:自分のトラッシュからポケモン1枚または基本エネルギー1枚を手札に戻す効果があります。本デッキではペパーによってこのカードをサーチ&利用する動きが盛り込まれています。例えば、中盤にオーダイルが倒されてしまった場合でも、「ペパーで夜のタンカを持ってきてトラッシュの水エネルギー1枚を回収」し、新たなオーダイルの育成に充てる…といった動きができます。また「ポケモンも1枚回収できる」ため、場合によっては倒されたオーダイルやミロカロスexそのものを手札に戻すことも可能です(再度ベンチに出し直して再進化を目指せます)。このように夜のタンカはリソース切れを防ぐ保険であり、いざというときに使えるよう1枚採用されています。ペパーでサーチ可能なので必要な時に引き込みやすい点も利点です。
- その他のグッズ:上述の他にも、もちろんデッキにはネストボールやレベルボール(種やHP90以下のポケモンを持ってくる)などのセッアップ用カード、ふしぎなあめ(ワニノコから一気にオーダイルに進化)、各種切り札となるグッズが採用されています。
特にポケギア3.0とカウンターキャッチャーはこのデッキの動きを支える重要なグッズと言えるでしょう。前者で安定性を高め、後者で逆転力を生み出すことで、序盤・中盤・終盤それぞれに隙の少ない構成になっています。
3. プレイングのポイントとテクニック
続いて、このデッキを実際に使う上でのプレイング(立ち回り)のポイントやテクニックについて解説します。序盤・中盤・終盤で意識すべきこと、そして対戦中に狙えるテクニカルな動きを順を追って見ていきましょう。
序盤の立ち回り: 展開優先と妨害の使い分け
最序盤(先攻1ターン目/後攻1ターン目)では、まず何よりベンチ展開を優先します。オーダイルのライン(ワニノコ→アリゲイツ→オーダイル)とミロカロスexのライン(ヒンバス→ミロカロスex)はそれぞれ最低1つずつ場に用意したいところです。ネストボールやレベルボールを使って、ワニノコとヒンバスを真っ先にベンチに出しましょう。同時に、ミミッキュやジーランス、スボミーといったサポートポケモンも状況に応じてベンチに置きます。
先攻の場合、攻撃はできませんが展開の猶予があります。ワニノコやヒンバスを出しつつ、可能であればミミッキュもベンチに置いておきたいです。ミミッキュは相手の次ターンの攻撃を牽制できますし、場合によってはバトル場に出してしまうのも手です(特に相手が次ターンにポケモンexで殴ってきそうな場合、ミミッキュを前に出せばダメージを受けずに済みます。エネルギーは基本的にワニノコかヒンバスに貼って育成開始します。先攻1ターン目は博士の研究などで手札を整えるか、ポケギア3.0で次のターン用のサポートを持ってきておきましょう。
後攻の場合、スボミーの活用を強く意識します。先述のようにスボミーの「むずむずかふん」は後攻1ターン目から撃てると強烈です。もし初手にスボミーが出せているなら、水エネルギーなどはあえて貼らず(スボミーは無エネで攻撃できるため)、そのままむずむずかふんを使いましょう。これで次の相手ターンのグッズを封じ、こちらの2ターン目にバトル場を明け渡します。
スボミーがない場合や出せない場合は、無理に妨害せず通常通り展開優先で構いません。後攻1ターン目にやりたいことの優先度は:「ベンチ展開」>「ドローサポートで手札補充」>「スボミーのグッズロック」くらいに考えておくといいでしょう。ミミッキュを先に出しておき、相手の2ターン目の攻撃をミミッキュで受ける構えを作っておくのも有効です。
序盤は基本的に山札圧縮と盤面セットアップです。ジーランスもこのタイミングでベンチに置いておきたいですが、最優先ではありません(中盤までに場に出ればOK)。エネルギーはワニノコとヒンバスにそれぞれ1枚ずつ貼るイメージで、手札にレアキャンディがあるならワニノコに集中させても良いでしょう。重要なのは2ターン目以降にオーダイルが動き出せる状態を作ることです。そのために必要なコマ(進化前ポケモンやサポート)は何かを考え、ポケギアやグッズを使って準備します。相手にサイドを先行される展開は織り込み済みなので、焦らずじっくり土台を作りましょう。
中盤以降の戦略: オーダイルの切り札運用とミロカロスexの使い所
中盤(だいたい自分の2~3ターン目以降)になったら、いよいよオーダイルで攻めるタイミングを見計らいます。理想的には自分の2ターン目にワニノコ→オーダイルへ進化(レアキャンディ使用)し、エネルギーが2個たまっていれば即「おおなみ」を放てます。無理に特性を使わずとも160ダメージは出るので、相手のバトル場に160以下で倒せるポケモンがいればそのまま倒してしまいます。例えば相手のたねポケモンVや進化前のHPの低いポケモンなどは、追加効果抜きで倒して数的有利を取りましょう。
相手のバトル場が硬い場合(160では倒れないポケモンexなど)や、一撃で倒しておきたいキーポケモンがいる場合は、思い切ってオーダイルの特性「トレントハート」を使うことも検討します。自傷ダメージ50は痛いですが、+120の火力は魅力です。ここでジーランスやマシマシラがベンチにいると、その後の展開がかなり楽になります。
オーダイルで一撃を決めた後、次のターンのプランを考えておくことが重要です。基本的に「おおなみ」を撃ったオーダイルは次のターン動けないので手に倒されなかった場合はジーランスの特性で「ぎゃくふんしゃ」を使って逃げるのがセオリーです。具体的には、オーダイル→アリゲイツの「ぎゃくふんしゃ」(30ダメージ&ベンチ下がる)を発動し、自らベンチに戻ります。
そしてバトル場には別のポケモンを出すわけですが、この時点でミミッキュが残っていればミミッキュを出すのが理想です。相手がポケモンexで反撃しようとしてもミミッキュにはダメージを与えられないため、その1ターンで再度オーダイルの攻撃準備を整えたり、別のポケモンで攻めることが可能です。
ミロカロスexの投入タイミングも中盤の鍵を握ります。相手のデッキにテラスタル持ちのアタッカーがいる場合、例えばドラパルトexやテラスタルリザードンexなどがメインなら、ミロカロスexをここで前線に出す判断もありです。特性「きらめくウロコ」でそれらからのダメージ・効果を完封できるため、相手は迂闊に攻撃できなくなります。ミロカロスexで前線を受け持っている間に、オーダイルをもう1体育てたり、手札を整えるといった動きができます。相手にとって嫌な壁を作り出しつつ、攻め手を絶やさないことがポイントです。
エネルギー運用としては、貼り替えの判断も出てきます。例えばオーダイルが一度倒されてしまった場合、次のアタッカーにエネルギーを集め直さねばなりません。基本水エネは毎ターン貼り、追加の加速にはリバーサルエネルギーやスーパーエネルギー回収(本リストでは夜のタンカで回収)を使います。ペパーを使えば、「夜のタンカ」でトラッシュから基本水エネルギーを回収→すぐそれを新たなポケモンに貼る、といった芸当も可能です。
中盤以降は1ターンの重みが増すため、途切れず攻撃できるかが勝敗を分けます。ミロカロスexのエネルギー要求は重いので、例えばオーダイルがまだ健在で殴れるうちはオーダイルに手貼り、倒されたらリバーサルエネルギーで即ミロカロスex起動、といったプランを事前に用意しておきましょう。特にリバーサルエネルギーは付けられる対象が「進化ポケモン(ルールを持つポケモンexは除く)」なので、ミロカロスexには貼れない点には注意です(ミロカロスexはルール上ポケモンexなのでリバーサル不可)。代わりにオーダイルやマシマシラには貼れるので、オーダイルの復帰やマシマシラへの悪エネ供給に使うといった使い分けが必要です。
マシマシラの特性も終盤の逆転に一役買います。例えば、トレントハートを使ったオーダイルが生き残っているなら、マシマシラのアドレナブレインでダメカンを相手に押し付けてからもう一度オーダイルで殴ることで、前のターンに逃したサイドを追加で取りに行ける可能性があります。終盤はお互いHPが低くなったポケモンが増えがちなので、ダメカン3個を動かす効果は思わぬフィニッシュ手段になります。相手のベンチで逃げたHP30のポケモンをマシマシラで仕留め、そのサイド1枚で勝利…という場面もあり得ます。
このように、逆転のためには複数のカードを組み合わせたプレイングが求められますが、それだけのポテンシャルがこのデッキには備わっています。特にナンジャモ+カウンターキャッチャーの動きは「決まればゲームをひっくり返す切り札」ですから、狙える場面ではぜひ狙っていきましょう。
4. まとめと応用
最後に、このデッキの総括と、どのようなプレイヤーに向いているか、さらに改良案や別構築のアイデアについて述べます。
このデッキの強みと弱点
強み:
- 爆発力と逆転力: オーダイルの最大280ダメージ+αという火力は、一撃で相手の主力を倒し得る破壊力です。加えてナンジャモ+カウンターキャッチャーのコンボなど、試合展開をひっくり返すギミックが豊富で、多少出遅れても逆転しやすいです。
- 守りの堅さとメタ性能: ミミッキュの特性によるexポケモンの攻撃無効化、ミロカロスexの特性によるテラスタル完封など、相手のデッキ次第では一方的に有利を取れる防御手段があります。これにより環境トップのデッキに対してメタゲーム的に強く出られる試合も少なくありません。
- サイド枚数コントロール: オーダイル自体は1サイドポケモンであり、他の採用ポケモンもほとんどが1サイド(ミロカロスexのみ2サイド)です。そのため相手にサイドを複数枚一気に取られる危険が少なく、サイドレースの計算がしやすいです。こちらはオーダイルで2枚取り、相手は1枚ずつしか取れない、といった展開になれば有利にゲームを進められます。
- 多彩なテクニック: ジーランスによる進化前ワザの活用、マシマシラによるダメカン転嫁、スボミーのグッズロックなど、テクニカルなプレイで相手の想定外の動きができます。対応力が高く、相手のプレイングを乱しやすいのも強みです。
弱点:
- 非ルールポケモンへの対応力不足: ミミッキュとミロカロスexという2大防御特性は、相手依存のため効果が刺さらないマッチアップがあります。
- ワザの継続性の低さ: オーダイルの「おおなみ」は連発不可という制約があるため、常に交互に高火力を叩き込むことはできません。一度攻めてから再度攻めるまでにワンクッション必要で、その隙に相手に立て直される危険があります。ジーランスで補ってはいますが、2体目のオーダイルや他のアタッカーが育っていないときにこの隙が生まれると、攻め手を切らしてしまう恐れがあります。
- 複雑なコンボゆえの不安定さ: デッキパワーは高いものの、かなめのカードがサイド落ちしたり序盤に引けなかった場合に脆さもあります。例えばレアキャンディが引けずオーダイルの進化が遅れる、悪エネルギーが来なくてマシマシラが置物になる、など。テクニカルなカードが多い分、噛み合いが悪いと単純なパワー不足になりかねません。また、各ギミックの成功可否がサイコロ(コイン判定)に依存しない点は良いのですが、その代わり状況依存なので、想定通りの劣勢にならないと発動できないカード(リバーサルエネやカウンターキャッチャー)が腐る可能性もあります。
- プレイ難度の高さ: 後述しますが、このデッキは扱いがやや難しいです。適切な場面で適切なカードを使わないと強みを活かせず、逆に下手に動きすぎると弱点を晒してしまいます。プレイヤーの習熟度によってパフォーマンスが大きく変わるデッキでもあります。
総合すると、ハイリスク・ハイリターンな要素を内包しつつ、多角的に攻め守りできるのがこのデッキの特徴です。環境に刺さればとことん強く、刺さらない相手には自分の腕前でカバーする必要がある、まさに大会向けの尖った構築と言えるでしょう。
どんなプレイヤーに向いているか
上記の強み・弱みからも分かる通り、このデッキは高度な判断力とプランニング力を要求します。したがって、以下のようなプレイヤーに特に向いているでしょう。
- 環境読みが好きなプレイヤー:ミミッキュやミロカロスexといったメタカードを活かすには、相手の主軸や環境の流行を把握していることが重要です。環境トップのデッキに合わせて自分の動きを変えたり、カード選択を調整したりするのが得意な人には、このデッキの柔軟性がフィットします。
- テクニカルなプレイを楽しめるプレイヤー:一風変わったカード(スボミーやジーランスなど)で相手を翻弄したり、コンボを決めて逆転したりするのが好きな人には打ってつけです。綿密に手順を組み立てて理想的な盤面を作り上げる達成感は、このデッキならではです。
- リスク管理が上手いプレイヤー:自傷ダメージや相手依存の特性など、扱いを誤るとピンチになる要素も多いです。ここぞという時に踏み込み、危険な時には撤退するメリハリを付けられる冷静な判断力が求められます。慎重かつ大胆なプレイングができる人向きです。
- 中〜上級者:初心者がいきなり使うには難易度が高めです。各カードの裁定やコンボの成立条件を理解しておく必要があります。逆に言えば大会で優勝できるほどのポテンシャルがあるデッキなので、腕試しをしたい中級〜上級者にはぜひチャレンジしてほしいデッキと言えます。