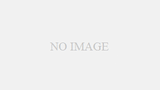「Nのゾロアークex」は、拡張パック「バトルパートナーズ」で登場した注目のカードです。本記事では、スタンダードルール環境における「Nのゾロアークex」の評価、採用されるデッキの種類や主な役割、相性の良いカードやコンボ、最新の大会実績やメタゲームでの立ち位置について詳しく解説します。
1. 現在の環境での評価と強さ
「Nのゾロアークex」は、1進化ポケモンながらHP280という高い耐久性を持ち、環境における生存率の高さが評価されています。また、その特性「とりひき」は、手札から1枚トラッシュし、2枚ドローするという効果を発揮し、デッキ内の不要カードやエネルギーを効率的に処理しつつ、必要なカードを引き込むドローエンジンとして機能します。
さらに、ワザ「ナイトジョーカー」は、ベンチに配置されている「Nのポケモン」のワザをコピーする能力を持ち、状況に応じた柔軟な攻撃が可能となります。ただし、コピーできるワザに依存するため、最大火力は「Nのレシラム」の170ダメージ程度となり、HP300超えの相手ポケモンexに対しては一撃で倒すには火力不足となるケースもあります。
そのため、デッキ構築上は「Nのレシラム」や「Nのヒヒダルマ」など、追加の火力補強カードの投入が求められ、全体としては**Tier3相当**の評価となっています。とはいえ、ドローと攻撃の二役をこなす汎用性の高さから、今後の研究次第で更に環境での存在感が高まる可能性も秘めています.
2. 採用されるデッキの種類と主な役割
現状、「Nのゾロアークex」は専用のNのゾロアークexデッキで主に採用されています。このデッキでは、ゾロアークex自体がドローソースとしてもメインアタッカーとしても活躍し、ベンチに配置した他のNのポケモンのワザを状況に応じてコピーしながら戦います。
例えば、序盤には特性「とりひき」で手札の整理とドローを進め、次に「Nのレシラム」や「Nのヒヒダルマ」と連携して攻撃の軸を作ります。このように、1体のゾロアークexが多様な役割を持ち、柔軟な攻撃プランを選択できる点が大きな強みとなっています。
また、モモワロウex採用型のデッキでは、モモワロウexの特性でゾロアークexをどく状態にし、後に「くさりもち」などのカードで火力を底上げするコンボが用いられます。一方、スタジアムを利用した「Nの城」採用型も存在するものの、ベンチに置いた他のNのポケモンが逃げにくくなるという欠点から、現在はあまり主流ではありません。
3. 相性の良いカードやコンボ
「Nのゾロアークexデッキ」では、以下のカードやコンボが特に効果的とされています。
- Nのレシラム:ベンチに配置し、ゾロアークexのコピー先として機能します。無条件で170ダメージを出す「イノセントフレイム」や、状況に応じた「パワーレイジ」との連携が、火力の柱として大きな役割を果たします。
- Nのヒヒダルマ:コピー用の要員として採用され、進化ポケモンながらも、ベンチポケモン狙いのワザで相手の展開を妨害する狙いが有効です。
- ペパー+なかよしポフィン+ワザマシンエヴォリューション:後攻の場合でも、初手からゾロアークexを盤面に整えられるコンボで、状況に応じた展開を可能にします。
- モモワロウex+くさりもち:モモワロウexの特性でゾロアークexをどく状態にし、くさりもちでダメージをプラスすることで、通常のコピー火力以上のダメージアップが狙えます。
- Nのポイントアップ:トラッシュした基本悪エネルギーを再活用できるグッズで、エネルギー管理とドローの安定性を高める重要なカードです。
- マキシマムベルト:ポケモンex専用のダメージアップカードとして、コピーした技の火力不足を補強する役割を持ち、状況に応じて与えるダメージを大幅に上昇させます。
これらのカードやコンボにより、ゾロアークexは柔軟かつ強力な戦術を展開できるため、環境に合わせた細かな調整が可能となっています。
4. 最新の大会実績とメタゲームでの立ち位置
最新のシティリーグ(2025年1~2月)の結果を見ると、「Nのゾロアークex」デッキは上位入賞するプレイヤーが現れ、シーズン3では優勝6回、準優勝10回といった実績を記録しています。これにより、トップメタデッキに対抗する一手として一定の信頼を得ていることが確認されています。
ただし、環境全体ではドラパルトexやタケルライコexといったデッキが依然として支配的であるため、「Nのゾロアークex」は現時点で**Tier3相当**のポジションに位置しています。環境が変動する中で、最適な戦い方や構築法が模索され続けているため、今後のカード追加や研究の進展により、さらに存在感を高める可能性があると言えるでしょう。
まとめ
「Nのゾロアークex」は、その高い耐久性とドローエンジンとしての性能、さらには柔軟なコピー技によって、スタンダード環境での活用の幅が広いカードです。一方で、火力面での限界や構築上の制約も存在するため、採用する際には「Nのレシラム」や「Nのヒヒダルマ」との連携、さらに補助カードの活用が不可欠です。最新の大会実績からも、確かな実力と今後の伸びしろが感じられるカードであることがわかり、引き続き注目すべき存在と言えるでしょう。